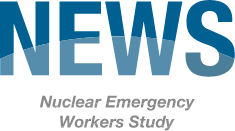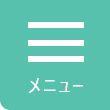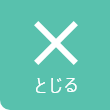全国に散らばる調査対象者の追跡の難しさ
- 溝上先生は令和 4 年度から緊急作業従事者の調査研究にも携わっておられますが、国立国際医療研究センター疫学・予防研究部長として以前から労働者のコホート研究(大規模な集団を追跡調査し、その対象者が晒される危険因子の健康への影響を評価するもの)である職域多施設研究、通称J-ECOHスタディをされていらっしゃいますね。
<溝上先生> - はい、J-ECOHスタディは関東・東海に本社を置く 10 数社の事業所で行われる約 10 万人の定期健康診断などの健康管理情報に基づく研究です。
働く世代に比較的多い、糖尿病や循環器疾患・がんなど疾病の発症、またはケガや病気による休業に関する予防要因を調べています。

- 働く世代を中心に対象としている研究という点では緊急作業従事者のコホート研究と同じように感じますが、これら 2 つの研究の相違点はありますか?あるとすればどのようなところでしょうか?
<溝上先生> - そうですね。J-ECOHスタディは、事業者が実施する受診率ほぼ 100 % の法定健診結果をオプトアウト(研究について情報公開し、データ提供に同意しない対象者はその旨を申し出る)という方法で研究に提供いただいています。このため対象となる方の情報を偏りなく収集することができます。
これに対して、緊急作業従事者の研究の場合は、全国にお住いの約2万人の方々に個別に呼びかけて、260 余りの健診機関で実施する健康調査(NEWS健診)にご参加いただくことによって成り立っています。
こうした全国規模で、しかもご本人の自由意志に基づく健診におよそ半数の方が参加され、開始から 10 年以上継続できていることは画期的なことだと思います。
- そうですね、10 年以上ご協力くださっている方々には感謝してもしきれませんね。
<溝上先生> - はい、ありがたいことです。この研究は 5 年間を 1 期とする労災疾病臨床研究事業で、1 期ごとに外部専門家による評価を受けています。第 2 期の令和 4 年度評価委員会では、対象者の方にいかに長期間ご協力していただくか?それが課題として指摘されました。
長期的なコホート研究で大切なこと
- なぜ長期間ご協力していただくことが必要なのですか?
<溝上先生> - その 1 つはコホートの規模に要因があります。例えば、広島と長崎にある放射線影響研究所が行ってきた原爆被爆者を対象とする寿命調査は約 12 万人を対象としています。
そのうち健康診断を中心とした成人健康調査は約 25,000 人を対象としています。これに対して、この研究では約 9,000 人の方にNEWS健診にご参加いただいています。
それなりの規模ですが、従来の放射線疫学調査と比べると大規模とはいえないため、統計学的に意味のある差をみつけるためには、長期に亘る追跡調査が欠かせないのです。

- ということは、現在の参加者人数では研究成果が出るまでには長い年月がかかるということですね。
<溝上先生> -そのとおりです。
- では、他にこの研究を進める上で課題となる点は何かありますか?
<溝上先生> - 被ばく線量の問題ですね。緊急作業従事者の方たちの場合は、国の政策で線量の限度を引き上げられましたが、厳格に被ばく量が管理されている下で、数日から数か月間作業に従事し、その間受けた放射線量は大多数が 10 mSv以下と低線量です。
したがって健康影響もそれほど大きくはないと考えられるため、統計学的に健康影響を検出するには、できるだけ多くの方に長期間ご協力していただく必要があります。
- そうすると、1 人でも多くの方に長期間ご参加していただきたいですね。そうして得られたデータを解析するためには何か留意すべき点はありますか?
<溝上先生> - この疫学研究では、放射線被ばくの影響を調べるために、亡くなられた原因やがんり患の状況を公的な統計資料(人口動態統計調査票、全国がん登録)を用いて追跡し、把握しています。ただ難しい点としては、放射線被ばく以外の様々な要因を考慮する必要があるということです。
たとえば喫煙や飲酒といった生活習慣、CT検査などの医療被ばくの履歴、健康との関連が深いといわれている社会経済要因などを把握することです。NEWS健診ではそうした要因についても質問票でお尋ねしています。
- なるほど。放射線の健康影響をみるには、その他の社会的な要因も考慮するために質問票にお答えいただくことが大切だということがわかりました。 それから、もうひとつ、死因やがんり患の調査という大切なお話がありました。この研究にご参加いただく際に、同意書をいただいているのですが、死因調査、がんり患調査に関しても同意をいただいているのですね?
<溝上先生> - そうです。ただ、現時点では、研究参加への意思表示を示していただいていない方が約半数おられます。しかし、本研究の成果には世界が注目していますので、私たち研究者は、疫学調査として偏りが少なく、科学的に妥当な結果を出すことが使命であると考えています。
このため、研究に参加された方だけを対象とする調査に加えて、緊急作業従事者全員を対象とする調査も進めていく必要があります。
- 死因調査、がんり患調査は緊急作業従事者全員を対象としていくべき、ということですね。
<溝上先生> - はい、緊急作業従事者全員に対して、国の人口動態統計調査票や全国がん登録などの既存の資料を活用した分析を進めることが必要となります。人口動態統計データの利用についてはオプトアウト(データ利用を本人が拒否できる機会を設けること)により倫理的な手続きを行っています。がんについては、対象者全員のデータ提供の可能性についてがん登録事務局に相談しているところです。
長期にわたる研究は受診者の健康管理にも
- オプトアウトという方法もあるということですね。ところで、私たちは研究に参加していただいた方たちからデータをいただいて研究を進めていますが、参加されている方たちには何をお返しできるのでしょうか?
<溝上先生> - まず、この研究は退職された後も続けて健診を受けていただけますので、2 年に 1 回の健診で、病気の早期発見・早期治療につなげていただけるものです。

- ご参加いただいたお一人お一人には、様々な情報提供をすることで、健康面を長期的に見守っていきたいと考えています。 さらに、私たちはこれからもNEWS健診だよりや、ホームページなどで、広く、研究成果を積極的に伝えていけるよう発信を継続していくつもりです。最後に研究参加者の方、そして、緊急作業従事者の皆さま方に向けて、一言お願いします。
<溝上先生> ― 研究参加者の方、そして、緊急作業従事者の皆さま方の健康管理に役立つ研究をしていきます。引き続きご協力をお願いします。